桜井甘精堂の歴史200年のあゆみ
小布施の栗の歴史は、今からおよそ六百年前の室町時代に始まるといわれています。
当時、この地方の領主だった荻野常倫が故郷、丹波国から栗をとりよせて植えたのが始まりと伝えられています。
小布施の土壌が栗の育成に適していたため、江戸時代にはすでにうっそうとした栗林が広がっていたということです。
小布施栗は品質がよく美味ということで、松代藩が毎年秋に将軍家に献上する習わしとなり、その名を天下に広めたといわれています。
この栗を用いて初めて菓子を作ったのが初代・桜井幾右衛門でした。
栗を粉にひいて作りあげたのが「栗落雁」。文化5年(1808)のことでした。画期的な「栗落雁」の創製によって、
二百年にわたる伝統を誇る栗菓子づくりがスタートしたのです。



新しい栗菓子の創製
「栗落雁」誕生から遅れること十年。文政2年(1819)には二代・武右衛門が「栗ようかん」を創製しました。
これらの栗菓子が誕生した文化文政期は、江戸の都市文化が急速に発展し旅行や料理、芝居など自由
でぜいたくな気分に満ちていました。この地を訪れた文人墨客も、きっと新しい栗菓子に舌鼓をうったことでしょう。
その後「栗落雁」は加賀藩や松代藩の御用菓子となり、江戸や京都に名を広めました。
また、元治2年(1865)には京都伏見宮家から裏菊御紋章の栗落雁調製を仰せつかり、記念の菊の御紋
入り衝立が今も残されています。
長く続いた大名公卿による「栗落雁」庇護も明治維新によって失われ、その後は「栗ようかん」が商品の
主流になりました。明治25年(1892)には五代・桜井佐七が「栗かの子」を創製し、全国に桜井甘精堂の
名を広めていきました。そして、この時から代々佐七を襲名して今日に至っています。
生菓子の「栗ようかん」「栗かの子」の販路を飛躍的に伸ばすことができたのは、大正8年(1919)に密閉式
ブリキ缶容器の開発に成功してからでした。しかし、第二次大戦中は砂糖の入手が不可能となり、栗林も
強制的に田畑に変えられ、ついに休業のやむなきに至り、製造再開は昭和24年(1949)のことでした。
その後もリンゴ生産におされて栗栽培が落ち込むなど苦難の道を歩みながらも順調に業績を伸ばし、
昭和41年(1966)には季節商品「栗もなか」を新たに加えベイシックな栗菓子のラインナップが完成しました。
創業以来二百年。時代の荒波の中で守り続けた栗菓子は、信州を代表する銘菓となりました。
その伝統の技と栗への情熱をベースに、新感覚の栗菓子づくりに積極的に取り組んでいます。
工場案内
北信五岳を中心とする北信濃の山々を遠望する展望絶景の地その名も栗ヶ丘に、敷地面積3000坪、敷地1500坪の工場は
、まず何よりも「安全、清潔」を目的として建設され、製造部署はクリーンルーム化されています。
また、大きな特徴として自動化倉庫(写真右側の黒の建屋)を備え、安全に作業ができる体制を整えています。


.jpg)
1.jpg)
条例で決められているとも聞くが、建物はすべて純日本建築漆喰壁による蔵造りの家屋が並ぶ
純粋なニッポンの心ががここに残っている・・・・・と叫びたくなってくるような町並みである
1.jpg)
.jpg)
1.jpg)
1.jpg)
文化施設も大小さまざまに点在している
1.jpg)
1.jpg)
1.jpg)
1.jpg)
1.jpg)
1.jpg)
小布施で北斎を語るとき、高井鴻山を抜きにしては語れない 代々豪農商の家に生を受けた鴻山は、
15歳から16年間京都や江戸で学び、幕末維新の激動期に時局に対応しつつ、
陽明学の教えに沿って”国利民福”の信条を貫いた人であると紹介されている。
北斎とは江戸遊学時代に交流があって北斎83歳の秋に小布施の鴻山を訪ねている
諸説あるが、天保改革の取り締まりを避けて小布施に向かったと思われる
鴻山が提供した「碧潴軒」を拠点に岩松院の天井画等肉筆画の世界に没頭した
尚、晩年は妖怪画を多く画いた
1.jpg)
1.jpg)
1.jpg)
1.jpg)
1.jpg)
北斎が起居したアトリエ
1.jpg)
1.jpg)
1.jpg)
小布施町は純粋に日本文化を維持しながら豊な生活環境を育てて来た町である
町の統計の数字からみても、この町が如何に住みよい豊な町であるということが伺える
世帯数 昭和30年 1.870世帯 平成21年 3.546世帯
人 口 昭和30年 10.450人 平成21年 11.455人
この数字から判断できることは、農業の衰退が叫ばれて人口の流出・減少が止められないのが
日本農村の悩みであるが、この町では50年間に世帯数は1,5倍に殖え、人口も増加している。
農産物構成をみると穀物は僅か10%程度で果樹が大半を占め、年齢構成も30歳台〜50歳台の層が厚い
これは米価に左右されず、国の補助金にも頼らず、栗をはじめ、農産物の加工販売に力を注ぎ
加えて観光資源をフルに活用した結果が物心ともに豊かな町を作り上げてきたのだろう
幾度でも訪れたい町である
牛に曳かれて
善光寺お参り

晦日の善光寺は善男善女で溢れていた
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
宿 坊
.jpg)
.jpg)
参詣者の賑わいを象徴する豪華な門前町
.jpg)
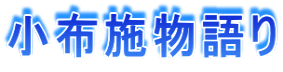


1.jpg)
1.jpg)
1.jpg)
1.jpg)
2.jpg)
1.jpg)
1.jpg)

1.jpg)
1.jpg)
.jpg)
.jpg)

1.jpg)
1.jpg)
1.jpg)
1.jpg)
1.jpg)
1.jpg)
1.jpg)
